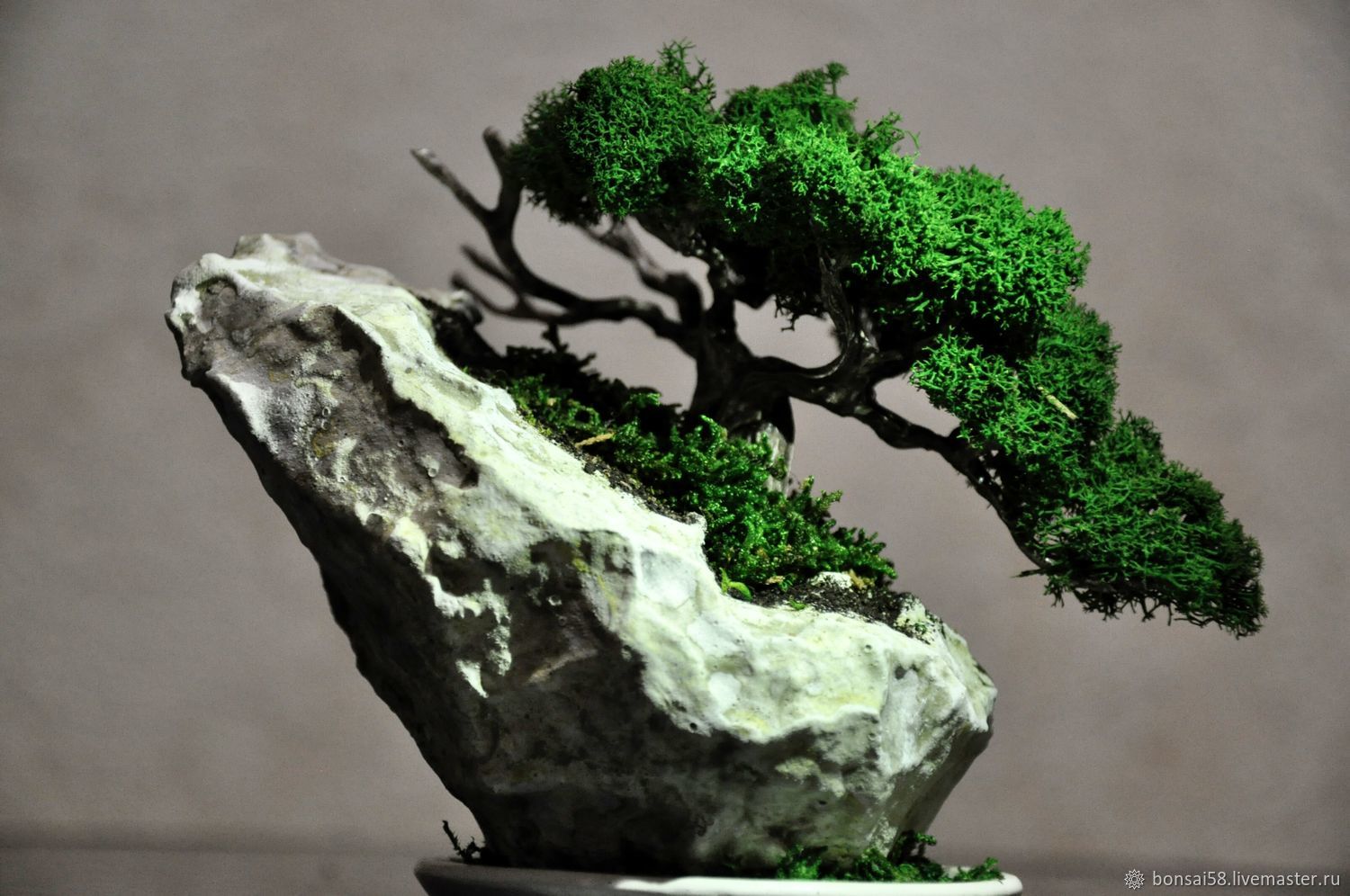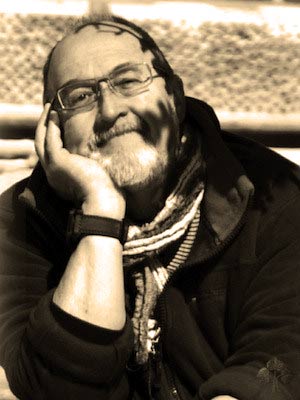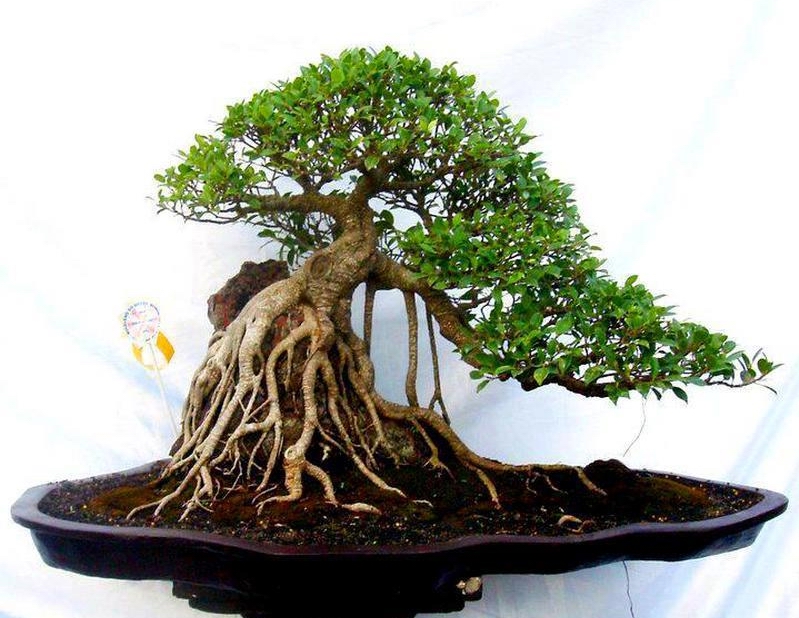鯉(原名:錦鯉(にしきごい)または日本の鯉は、色の斑点がある多色の魚で、家庭で特別に飼育され(最大6種類)、特定のカテゴリに割り当てられています。鯉の元となった鯉は、中央アジア、ペルシャが起源であると考えられています。しかし、古代の錦鯉の遺跡が日本で発見され、鯉が自然に日本に生息していることを示していることも心に留めておく必要があります。
鯉は中国原産で、贈答品として日本に持ち込まれました。日本で鯉に関する最初の記録は西暦71年に遡ります(景行天皇が鯉を飼っていたとされています)。しかし、鯉が突然変異を起こし、現代の錦鯉として認められる色彩を獲得したのは19世紀になってからでした。

鯉の起源
鯉の発祥地は、新潟県山古志村(現在の長岡市)です。この山岳地帯では、入植者たちが山を切り開き、米や野菜を育てるための「棚田」が作られました。水田の上には灌漑用の池が作られ、鯉はそこで食用として飼育されていました。ところが、ある日突然、鯉に突然変異が起こり、黒い鯉の中に様々な色や模様の鯉が泳ぐようになりました。
養殖業者たちはこれに驚き、変異した魚を食べなくなり、より美しくユニークな鯉を育て始めました。
この突然変異した鯉は当初、地元の人々の間で人気を博しましたが、すぐに他地域の人々が取引するようになり、原産地をはるかに超えて広く知られるようになりました。その結果、錦鯉の養殖は魚愛好家にとっては趣味となり、農家にとってはビジネスとなりました。
鯉コンテンツ
錦鯉は一般的な淡水魚で、水温8~35℃で生息できます。ただし、最適な水温は約22℃です。鯉のいる池は、高温や低温への適応を促進するため、少なくとも1メートルの深さが必要です。鯉は雑食性ですが、鮮やかな色彩と良好な発育を得るには、適切な栄養管理が非常に重要です。錦鯉は餌を貯蔵することができないため、定期的な給餌(1日に最大6回まで)が特に重要です。鯉の平均寿命は約70年ですが、中にはそれよりもはるかに長生きする個体もいます(最長寿の鯉は226年生きました)。
日本の鯉の種類
現在、日本の鯉には80種類以上が存在し、そのうち26種類は共通の特徴によってグループ分けされています。最も人気のあるのは、紅白、大正三色、昭和三色からなる御三家です。現在も新しい品種の開発が活発に行われています。鯉の「品質」は、体の形だけでなく、色の明るさやコントラストによっても左右されます。